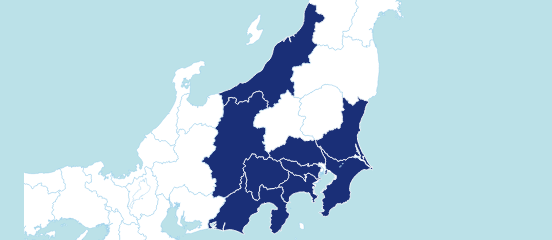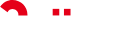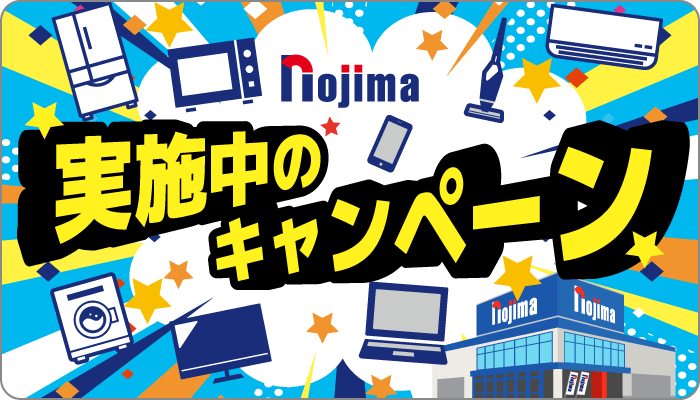今年の節分は豆まきを楽しんでみませんか?
更新日時 : 2021-06-02 17:33
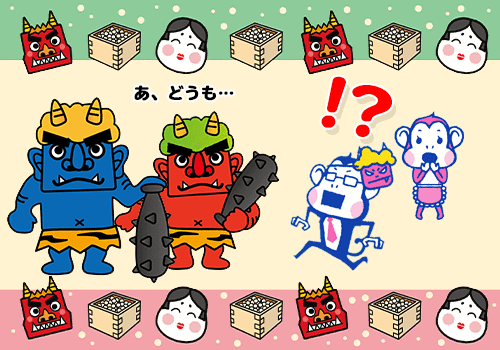
2月3日は節分ですね。
節分のイベントと言えば豆まきですが、実は豆まきをしなくてもいい人がいるのはご存知でしょうか?
そこで今回は、意外と知らない豆まきの由来や豆知識などについてまとめてみました。
節分とは
本来節分は季節を分けると書くように、季節の節日である立春・立夏・立秋・立冬の前日を指す言葉でした。
しかし、昔の日本には春を一年の初めとする考え方があり、冬から春に変わる立春の前日だけを節分と呼ぶようになりました。
立春が一年の初めなので、節分は大みそかにあたりますね。
豆まきの由来は?
豆まきの由来は諸説あります。
季節の変わり目、特に年の変わり目には邪気(鬼や魔物)が入りやすいと考えられていました。
そこで、邪気を払う追儺(ついな)という、鬼役の人を弓矢などで追い払う儀式が行われていました。
またそれとは別に、平安時代には豆打ちという儀式がありました。
これは、年の変わり目には家の恵方(縁起のいい方角)の部屋を豆で清め、その部屋に移るというものです。
この追儺と豆打ちがいつのころか融合して、室町時代には現在の豆まきに近い形で武家の間に広がったという説があります。
一般庶民に広まったのは、江戸時代頃だと言われています。
なぜ炒った豆をまくのか?
こちらも諸説ありますが、五穀の一つである豆には、邪気を払う霊力があると信じられていました。
また魔を滅するという意味で魔滅(まめ)、外にまいた豆が発芽するのは縁起が悪い(魔芽)ということから、炒った豆を使うようになったという説があります。
現在では、まいた後の事を考えて、小袋に入れ小分けにしたり、殻つきの落花生を投げる地域もあるようです。
豆まきの正しいやり方とは?
地域によってやり方や掛け声に違いはありますが、一般的なやり方は以下の通りです。
夜に行う
鬼は夜にやってくるとされています。
鬼や邪気は暗い場所を好むそうです。
豆をまく人
一家の主が豆をまきます。
また地域によっては年男や年女、厄年の人がまく事もあるそうです。
まき方
まず窓や玄関を全て開け、鬼は外と言いながら外に向かって豆を投げます。
追い出した後は鬼が入ってこないよう、窓を閉めます。
その後、福は内と言いながら部屋の中に豆をまきます。
部屋の奥から、だんだん玄関に近づくようにしていき、最後に玄関を閉めます。
まいた後の豆
一年の厄除けの願いを込め、自分の年齢よりひとつ多い数を食べます。
あらかじめビニールシートを敷いておくと楽に片付けられます。
また掃除機の吸い込み口にガーゼを付けると、楽にとる事ができます。
もし食べる際には、しっかりと洗ってください。
現代では
しかし現代では、家族で行うイベントの一つという見方が強く、大人が鬼役となり子どもが豆を投げるというやり方が思い浮かびますよね。
そこで必要になるのが、鬼のお面です。
鬼の顔を自宅のプリンターで印刷した手作りお面で、手軽にイベントとして楽しんでみるのもいいかもしれません。
そんな鬼のお面をプリントできるサイトを、いくつかご紹介します。
鬼のお面を印刷できるサイト

絵の形に切って、輪ゴムを使ってお面にします。
厚手の紙に印刷すると、しっかりしたお面になりますよ。
豆まきの豆知識
豆まきをしなくてもいい人がいる?
実はワタナベ姓の方は、豆まきをしなくてもいいそうです。
その理由は、鬼が怖がって近づかないからです。
平安時代、源頼光(みなもとのよりみつ)は、暴れまわる鬼を退治するため、討伐隊を結成し、鬼退治に向かいます。
そこで活躍したのが、討伐隊の一人である渡辺綱(わたなべのつな)でした。
渡辺綱は鬼の腕を切り落とし、その強さは鬼たちに衝撃を与えました。
それ以来、鬼は渡辺一門を恐れ、その子孫も含め、ワタナベ姓に近づかなくなったそうです。
ワタナベ姓の家では、掛け声は福は内だけだったり、鬼を閉じ込めるために鬼も内と言うところもあるそうです。
鬼はなんで虎のパンツ?
鬼門という言葉をご存知でしょうか。
鬼門は鬼が出入りする方角で、北東にあたります。
また、昔は十二支を使って方角を表していました。
北東を表す十二支は、丑寅(うしとら)。
そのため、牛のツノと虎のパンツとなったそうです。
メディア(家電小ネタ帳®)に関するお問い合わせ
お問い合わせ人気記事ランキング
-
1位

【2025年】ドコモ新料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ mini」とは?旧プランとの比較も
-
2位

【一眼レフ並み!】カメラ性能が高いスマホをランキング形式でご紹介
-
3位

【2025年版】auの料金プランを徹底比較!一覧やおすすめプランをご紹介
-
4位
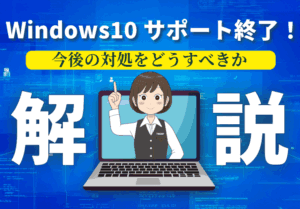
【2025年10月まで】Windows10サポート終了!期限延長やどうすればいいのか解説
-
5位

VAIO 最新ノートパソコン実機レビュー|使ってわかった評判とおすすめ機種
関連記事
-
 2025.5.2
2025.5.2【2025年】 母の日はいつ?ギフト・プレゼントに何...
-
 2025.2.28
2025.2.28ひな祭りとは?意味や由来、歌詞、食べ物、飾りなどを紹...
-
 2025.2.6
2025.2.6バレンタインデーの由来は?いつ?海外との違いや本当の...
-
 2025.1.31
2025.1.312025年の節分は2月2日!恵方巻・豆まきの由来や方...
-
 2024.12.20
2024.12.20グアム旅行の費用やおすすめ時期は?観光スポットや持ち...
-
 2024.12.14
2024.12.14大掃除のやり方のコツは?順番や必要なもの、チェックリ...
-
 2024.12.25
2024.12.25【2025年巳年】年賀状印刷はノジマがおすすめ!干支...
-
 2024.8.23
2024.8.23【雷対策】雷サージからコンセントを守るには?パソコン...
-
 2024.6.20
2024.6.20【2024年】今年の父の日はいつ? 由来や始まった時...
-
 2024.11.22
2024.11.22【神奈川県】ノジマも参加!「はじめてばこ」とは?気に...
-
 2024.2.27
2024.2.27【速報】大谷翔平選手のオープン戦、生中継放送が決定!...
-
 2025.3.28
2025.3.28CES2024現地レポート!最新家電など見どころをご...
-
 2024.1.26
2024.1.26【速報】日経社歌コンテスト2024でノジマが第2位&...
-
 2023.12.31
2023.12.31【井上尚弥vsタパレス戦】Leminoで完全無料で試...
-
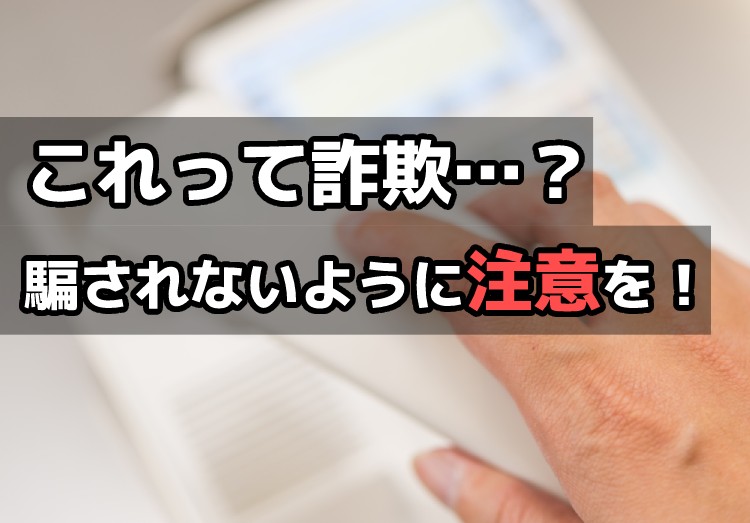 2023.11.29
2023.11.29【注意】詐欺の種類を解説|Amazon、佐川急便詐欺...
-
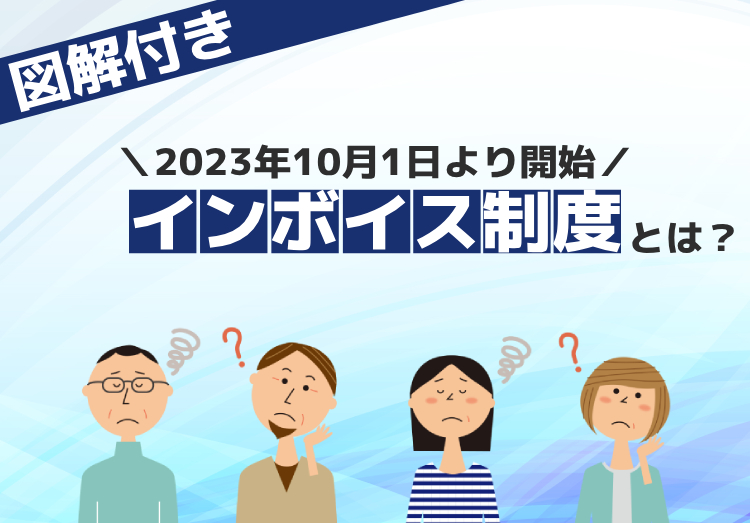 2023.9.30
2023.9.30インボイス制度とは? わかりやすく個人事業主、免税事...
-
 2023.9.6
2023.9.6ポイント付与終了!【第3弾】かながわPayまとめ!使...
-
 2024.11.11
2024.11.11モバイルバッテリーの正しい捨て方を解説!回収ボックス...
-
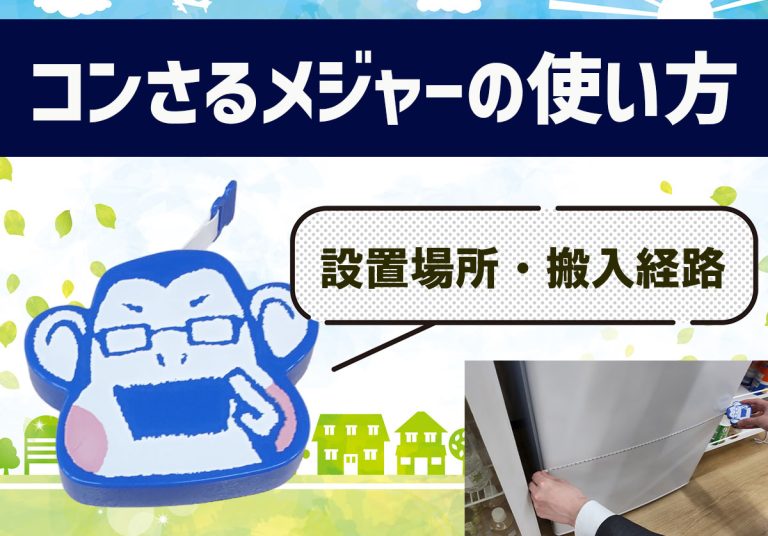 2023.6.22
2023.6.22コンさるメジャーの使い方!設置場所・搬入経路の測り方...
-
 2023.7.3
2023.7.3大雨対策のポイントと備え方!大雨警報と注意報の違いも...
-
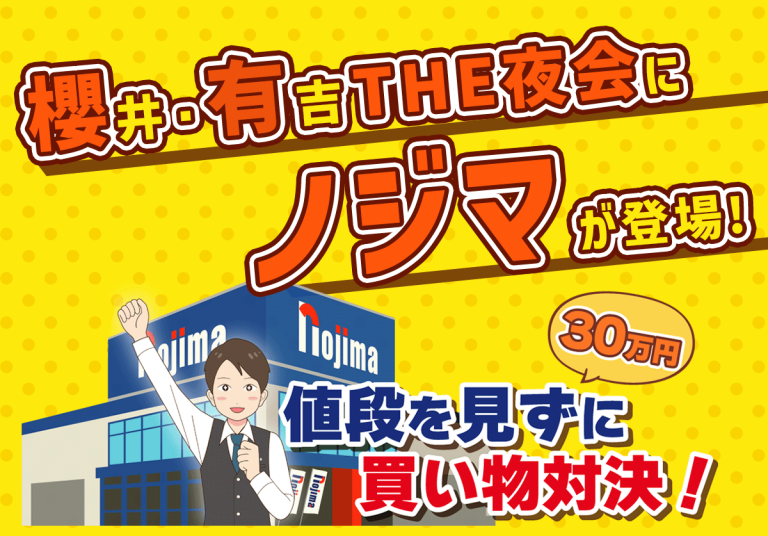 2023.10.20
2023.10.20【6/15放送】TBSテレビ「櫻井・有吉 THE夜会...
-
 2025.3.26
2025.3.26黄砂とは?時期はいつからいつまで?原因や症状、対策方...
-
 2023.3.16
2023.3.16新生活家電セットおすすめ!一人暮らし向けや安いセット...
-
 2025.1.17
2025.1.17新生活に必要なものは?家電と日用品・消耗品のチェック...
-
 2025.3.7
2025.3.7家庭でできる地震対策方法|防災グッズや地震時に取るべ...
-
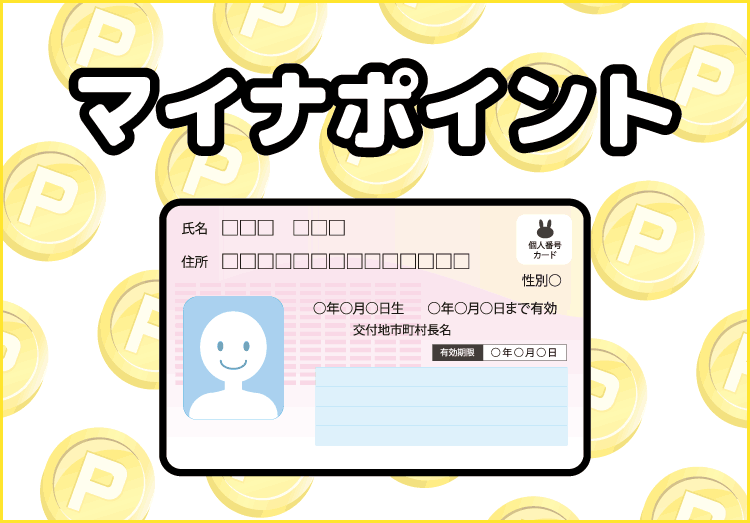 2023.4.7
2023.4.7【ポイント付与期限が9月末まで延長】マイナポイント最...
-
 2023.5.4
2023.5.4マイナンバーカードの申請方法まとめ!ポイントのもらい...
-
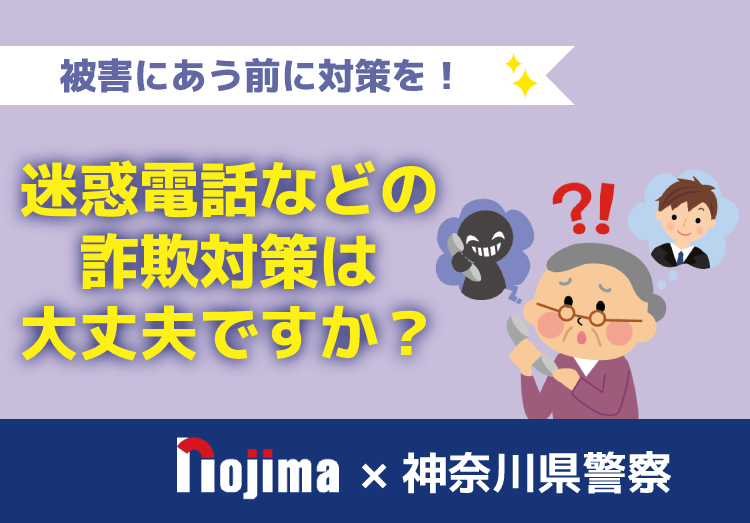 2023.2.1
2023.2.1特殊詐欺とは?最新の手口と電話機での対策方法を解説!
-
 2022.10.3
2022.10.3【新発表】Wi-Fi 6E対応ルーターとは?NECの...
-
 2023.7.31
2023.7.31台風への備えが必要な理由は? 買い物で備えるものや防...